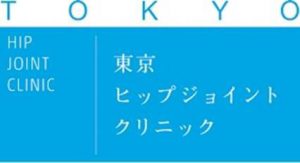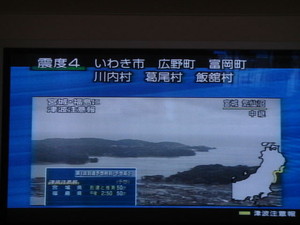[私の知り合いであり、尊敬する人物でもある方からのメッセージです]
|
白杖を持つまで ・・・ 私は医師から網膜色素変性症の告知を受けた後は、定期的に医師の診察を受けるように指示されていました。しかし、受診しても何の手立てもなく、悪化する時期を待つだけのように感じていたので、ほとんど受診することなど有りませんでした。医師の診察を受けようと感じたのは、就職して理学療法士資格を得る為の夜間学校へ通学が始まって間もなくのことでした。急に物が見えにくくなったように感じられたからです。就職直後の視力は右0.1・左0.2でしたが、受診しての視力検査では、右0.05・左0.07となっていました。医師の説明では、病気によって眼を酷使することによって病気の進行は速まる。そしてこの病気では光の乏しい中での文字を読み書きすることは、眼を酷使することに該当すると教わったのです。この診察以後は、医師の元に通うことが一つの定例行事となったのです。私は就職以前に、鍼灸・按摩・マッサージ・指圧の免許を取得する為に、都内阿佐ヶ谷駅近くの厚生省管轄の国立東京視力障害者センター(元東京光明寮)中途視覚障害者施設で、1969年4月から1972年3月まで学習しました。その学習の中に、歩行練習も入っており、指導教官に白杖を使っての歩行指導を受けたことを覚えています。しかし、就職しても結婚しても子どもに恵まれても、白い杖に頼ることなどなく、悪化している視力での独歩歩行で子どもと遊んでいました。これを読まれている晴眼者には、視力0.05・0.07の視力で独歩歩行が可能かと疑問を感じるでしょうが、後天性で徐々に視力が低下した私には、充分行動可能な視力なのです。それでも徐々に視力低下が進み、0.01・0.02となったときには、行動の自由は束縛され始めたのです。行動の自由が奪われるようになると、歩行していて対面者を避けることができなくなり、衝突するようになったのです。このような事実を医師に話すと、「え、白杖を使っていなかったの・・・?」と驚かれ、即、白杖を使うように言われました。その事で、「白杖を持つのは、自分の行動を助けるだけでなく、他の人に視覚障害者であることを知らせる意味がある」と説明を受けたのです。後に知ったことですが、この杖を持つことによって次のように法で保護されることとなっていたのです。 |
|||
|
●道路交通法 1(目が見えない者、幼児、高齢者等の保護) 第十四条:目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む 以下同じ)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。2目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。(運転者の遵守事項) 第七十一条:車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。二 身体障害者用の車いすが通行しているとき、目が見えない者が第十四条第一項の規定に基づく政令で定めるつえを携え、若しくは同項の規定に基づく政令で定める盲導犬を連れて通行しているとき、耳が聞こえない者若しくは同条第二項の規定に基づく政令で定める程度の身体の障害のある者が同項の規定に基づく政令で定めるつえを携えて通行しているとき、又は監護者が付き添わない児童若しくは幼児が歩行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行又は歩行を妨げないようにすること。二の二 前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の歩行者でその通行に支障のあるものが通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること。 ●道路交通法施行令 (目が見えない者等の保護) 第八条:法第十四条第一項 及び第二項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。2 法第十四条第一項 の政令で定める盲導犬は、盲導犬の訓練を目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第三十一条第一項 の規定により設立された社会福祉法人で国家公安委員会が指定したものが盲導犬として必要な訓練をした犬又は盲導犬として必要な訓練を受けていると認めた犬で、内閣府令で定める白色又は黄色の用具を付けたものとする。3 前項の指定の手続その他の同項の指定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。4 法第十四条第二項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。5 法第十四条第二項 の政令で定める用具は、第二項に規定する用具又は形状及び色彩がこれに類似する用具とする。このように法や施行令で保護されていても、また医師から白杖を持つように言われていても、私は白い杖を持つことを躊躇していたのです。〔白杖を持っていると周囲の人に注目されるのではないか?〕と思うのでした。でも、白杖を使い慣れてくるに従い、自己の思いが間違えであったことを知らされたのです。
|